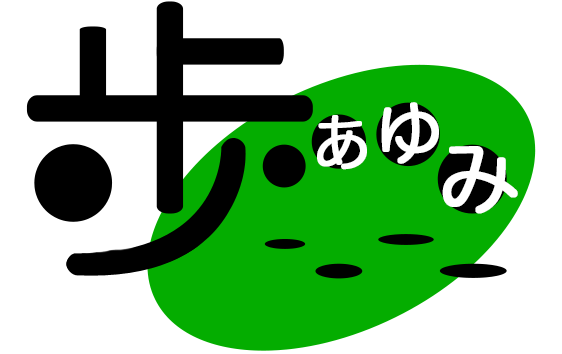こんにちは!就労継続支援施設B型 歩の大波です。
「就労選択支援って何?」「いつから始まるの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
就労選択支援は、障がいのある方が自分に合った働き方を選べるように支援する、新たな制度です。
今回は、その制度の概要や対象となる方、利用の流れまでをわかりやすくご紹介します。
これから就労継続支援A型やB型の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

目次
就労選択支援をわかりやすく解説!
就労選択支援とは、障がいのある方が自分に合った就労先や働き方を選べるよう、専門的なアセスメント(評価)を通じてサポートする障害福祉サービスです。
2022年の障害者総合支援法の改正により創設され、2025年10月1日からの開始が予定されています。
就労選択支援の目的
この制度の最大の目的は、障がいのある方が主体的に働き方を選べるよう支援することです。
実際に就労移行支援や継続支援A・B型を利用する前段階で、自分の希望や特性を整理し、将来の選択肢を明確にする“入口支援”としての役割も担っています。
従来は、利用者の希望や特性に合わないサービスにつながってしまったり、一度始めたサービスから次のステップに進みにくいといった課題がありました。
就労選択支援では、次のような取り組みを通じて支援を行います。
- 実際の作業を体験し、スキルや適性を確認
- 面談により希望する働き方や必要な配慮を整理
- 医療機関やハローワークなどからの意見も取り入れて総合評価
- 地域の雇用状況や利用可能なサービスを案内
このようなプロセスを経て、自分に合った働き方や進路を見つけることができます。
対象となる方は?
就労選択支援の対象は、就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)の利用を検討している方、または現在利用中の方です。
また、特別支援学校の高等部に通う生徒も対象となっており、卒業後の進路選択をサポートする制度として活用できます。
【重要ポイント】
2025年10月以降、就労継続支援A型・B型を新たに利用する際は、原則として就労選択支援の利用が必須となります。
ただし、A型および就労移行支援については、2027年4月以降に段階的に対象が広がる予定です※。
※本人の体調や過去の利用歴、地域の体制などに応じて、市区町村が必要と認めた場合は対象外となることがあります
どこで利用できる?
就労選択支援を受けられるのは、以下のような機関です。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター
- 自治体が設置する就労支援センター
- 障害者職業能力開発訓練事業所 など
ただし、全ての事業所が提供できるわけではありません。
過去3年以内に3人以上の一般就労者を送り出した実績など、一定の要件を満たした事業所のみが実施できます。
利用期間はどのくらい?
利用期間は原則1カ月間で、必要に応じて最長で2カ月間まで延長が認められています。
短期間に集中的なアセスメントを行うことで、自分に合った進路を効率良く見つけることが可能になります。
就労選択支援のサービスを詳しくご紹介!
就労選択支援で受けられるサービスについても、具体的な内容をお伝えします。
就労アセスメント
就労選択支援の目的は、就労の可否を判断することではなく、どのような働き方が自分に合っているかを見極めることです。
賃金や生活スタイル、勤務頻度などの希望を確認した上で、データ入力やラベル貼りといった軽作業を体験し、その作業を通して専門スタッフが能力や適性、必要な配慮を整理していきます。
ケース会議・アセスメントシートの作成
期間中には、利用者・ご家族・支援機関が参加するケース会議が開かれ、アセスメント結果をもとに今後の進路を検討します。
面談や作業の様子から得られた情報は「アセスメントシート」にまとめられ、働き方の検討に活用されるほか、自分の現状や課題を客観的に理解する材料にもなります。
関係機関との連携
アセスメント結果をもとに、必要があれば就労支援機関や教育機関、ハローワークなどと連携して調整を行います。
この連携によって、見学や実習などの機会が広がり、より多くの選択肢の中から最適な進路を見つけやすくなります。
就労選択支援を利用する場合の流れも確認
就労選択支援を利用する際の基本的な流れをご紹介します。
①市区町村への相談・申請
まずはお住まいの市区町村の役場の障害福祉課などに相談し、利用申請を行います。
②サービス等利用計画案の作成
相談支援事業所またはご本人が「計画案」を作成し、提出します。
③支給決定
自治体による審査を経て、支給が決定されます。
④就労選択支援の利用開始
支給が決まった事業所でアセスメントや作業体験を行います。
⑤進路の決定と申請
アセスメント結果を踏まえて希望する就労先や支援サービスを選び、必要な申請を行います。
就労後も希望に応じて再度、就労選択支援を利用することができるため、状況の変化に応じて柔軟に対応が可能です。
なお、就労に関する悩みや不安を抱えている方には、さまざまな支援制度が用意されています。
こちらのコラムでも詳しくご紹介していますのでぜひあわせてご覧ください。
うつ病で社会復帰できない(怖い)と悩む方が無理なく進める方法
就労選択支援は、これらの支援制度の入口として、どの道筋が最適かを見極める重要な役割を担っています。
就労継続支援B型を利用する予定なら「歩」にもご相談を

私たち就労継続支援施設B型「歩」は、精神保健福祉士、キャリアコンサルタント、介護福祉士など、専門スタッフが常駐し、体調や生活リズムに応じて、無理なく働くペースを一緒に整えていける環境です。
「短時間から働きたい」
「生活リズムを整えたい」
「いずれは一般就労も目指したい」
そんな想いをお持ちの方を、あたたかくサポートさせていただいています。
就労選択支援やそのほかにも不明点があれば、なんでもお答えします!
軽作業などの就労訓練を通じて、少しずつ働く感覚を取り戻しながら、自分らしいペースで社会とのつながりを築いていきましょう。
JR手稲駅から徒歩3分というアクセスしやすい場所にあり、見学も随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお越しください。
就労選択支援の利用で自分に合った働く環境を見つけよう
就労選択支援は、2025年10月から始まる新しい支援制度で、障がいのある方が自分らしい働き方を主体的に選べるよう後押しします。
1〜2カ月のアセスメントを通じて、利用者様ご本人の特性や希望を詳しく把握し、最適な就労先や福祉サービスの選択をサポートします。
今後はA型やB型の新規利用にはこの制度の利用が原則となるため、制度の内容をきちんと理解しておくことが大切です。
利用者様の主体性を重視し、さまざまな選択肢の中から本当に合った進路を見つけられるこの制度により、より多くの方が自分らしい働き方を実現できるようになるでしょう。
就労継続支援施設B型「歩」は、障がいのある方がご自身に合った働き方を見つけるお手伝いをしています。
就労選択支援に関するご質問や、就労に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。